
太りすぎたのでダイエットをしたいと考えています。
ダイエットにはどんな方法があるのか知りたいです。
ダイエットをしよう!
そう意気込んでみても、実際どのようにすれば痩せるのかってよくわかりませんよね?
とにかく食べなければ痩せるの?
カロリーの制限は必要?
脂を減らせばいいの?糖質制限ってなに?
上記のような疑問に対して、答えながら、ダイエットの方法やその種類、ダイエットを成功させるための考え方についてお話していきます。
ダイエット方法の種類


ダイエットの方法には、様々な物があります。
ダイエットの基本は、一日に消費するエネルギーを一日に摂取するエネルギーが超えてしまわないように食事を制限することですが、その制限の方法に種類があります。
よく知られているダイエットの方法としては、ローファットダイエット(脂質制限)、ローカーボダイエット、ケトジェニックダイエットなどがあります。
これらについて見ていきましょう。
ちなみに僕自身は、コンテストに向けての減量時などでローファットダイエットとケトジェニックダイエットを中心に実施しています。
ローファットダイエット
ローファットダイエットとは、3大栄養素であるタンパク質、脂質、炭水化物のうち脂質を特に抑えて行うダイエットを指します。一般的なカロリー制限ダイエットがこれにあたります。
一日に食べられるカロリーを設定した後、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の割合を、3:2:5程度に計算し、食事を決めていきます。
炭水化物を多く食べられるため食費がかさまず、栄養バランスが崩壊しにくく、制限の範囲内であれば特に何を食べても大丈夫なダイエットですので、比較的精神負担は少ないダイエットと僕は考えています。
その反面、炭水化物を多く食べることから、食べるものや食べるタイミングに注意をしないと、血糖値の上がり下がりが大きく生じるため、空腹感や食後の眠気などを感じやすいダイエットとも言えます。
上記のデメリットはありますが、あまり特殊なことをする必要はなく、行いやすい基本的なダイエット方法と言えます。


ローカーボダイエット
ローカーボダイエットとは、ローファットダイエットと違い、炭水化物の割合を抑えて行うダイエットです。タンパク質は体にとってとても大切な栄養素ですので、どのダイエット方法でも基本的に量は変化させません。
割合としては、P:F:C=3:5:2 程度でしょうか。多少の炭水化物、糖質は食べることができますが、主な活動エネルギーは脂質から得るダイエットのため、肉や魚、ナッツなどを多く食べる必要があり、ローファットダイエットと比べると食費が嵩みやすい傾向にあります。
また、中途半端に糖質を摂ってしまうことから、ローファットダイエットや後述するケトジェニックダイエットと比較して糖新生という現象が生じやすい(筋肉を分解してエネルギーを得ようとする)、ダイエット後の代謝が落ちやすくリバウンドしやすいと言われています。
また、揚げ物が食べれるダイエットのように見えますが、衣に含まれる炭水化物の量や、油の質を考えるとおすすめはできません。
上記のデメリットは考えられますが、脂質を多く摂ること、血糖値の上下が少ないことから空腹感を感じにくいこと、体重の落ちるペースはとても早いことがメリットとして挙げられますので、とにかく体重だけをなんとか落としたいというような場合には有効かもしれません。
ケトジェニックダイエット
ケトジェニックダイエットとは、ローカーボダイエットのように糖質の割合を抑えるダイエットです。
ローカーボダイエットと違う部分としては、原則として炭水化物のうち糖質を極力一切摂らないようにするという点があります(食物繊維は可)。
調味料や野菜などでどうしても摂ってしまう糖質を考慮して、三大栄養素のバランスとしてはP:F:C=3:6:1程度になります。(考え方としては、3:7:0にするイメージですが)
体や脳で使いやすいエネルギーである糖質を一切摂らないことで、代わりに体脂肪や脂質を効率良くエネルギーとして使えるようにケトン体というものに変換(代謝)することで脂肪を燃焼させ、ダイエットをするといった仕組みの方法です。
ローカーボダイエットのように食費がかさみやすい他、非常に厳しい糖質制限のため、炭水化物が好きな人にとっては精神負担が大きいこと、体脂肪、摂取した脂質からケトン体を作り、エネルギーとして利用できるケトーシスという状態に体がなるまで、このダイエットの経験が少ない人ほど時間がかかり、ケトーシスが安定するまでは下痢や倦怠感などの体調不良に襲われる可能性があることなどのデメリットがあります。
他のダイエット方法よりもデメリットが大きく見える一方で、ケトーシスが安定しさえすれば、エネルギーとして使うものが糖質からケトン体になる関係で、ローファットダイエット、ローカーボダイエットと比較しても糖新生は起きにくいため、筋肉の分解が起きにくかったり、血糖値の上下がほぼ起きないため、食後の眠気が非常に起きにくいこと、その他ケトン体は健康に良いという報告が多数されていることなどもありメリットの部分も非常に大きいダイエット方法です。
他2つのダイエット方法と違い、脂肪を燃焼してエネルギーを作る体質に変えるようなダイエット方法であるため、糖質さえしっかりと制限していれば、カロリーに関してはそこまで強く気にする必要はない(まったく無視していいわけではない)という点でも、特徴があります。
糖質さえなければ、毎食焼き肉やステーキでも良いという点では、脂っこい肉が好きな人や、もともと炭水化物をそこまで摂る習慣のない欧米人などに向いている方法かもしれません。
ただし、食材や調味料ごとにどれくらい糖質が含まれているか、何が食べれて何が食べられないのかなど、考える事柄が多いので、あまり初心者向けではありません。


ダイエットにおけるカロリー計算について


ダイエット方法によって重要度は変わりますが、既に述べたように、ダイエットにおいて、食事から摂取するカロリーを自分の消費エネルギーが上回る必要があるという点はどの方法でも変わりません。
ここでは、カロリーの計算についてお話していきます。
基礎代謝を知る
自分の1日の消費エネルギーは
基礎代謝 + 活動代謝
で表されます。
基礎代謝とは、簡単に言えば1日何もせずに寝ていても消費されるエネルギーのことで、生きるために必要な最低エネルギーのことを指します。
基礎代謝の計算方法はいくつかありますが、個人的には臨床場面などでもハリスベネディクト方程式を用いることが多いです。
計算式は
- 男性: 13.397×体重kg+4.799×身長cm−5.677×年齢+88.362
- 女性: 9.247×体重kg+3.098×身長cm−4.33×年齢+447.593
です。
かなり複雑な方程式なので、こちらの計算サイト(Ke!san)を使用することをおすすめします。
また、上記の式は筋肉量と体脂肪量に個人差があることは計算されていないので、体組成計などで表示される基礎代謝量も参考にするといいかもしれません。



僕の場合、基礎代謝は1,846kcalです。
1日寝たきりでも消費されるエネルギーが基礎代謝なので、
これを下回ると生命活動に必要なエネルギーが不足しているということになります。
ダイエットにおいてカロリーを制限することは重要ですが、基礎代謝を下回ってしまうような食事内容の場合、エネルギーが不足しすぎてしまうことが考えられます。
健康被害も十分に考えられますので、ここで計算した基礎代謝量をを下回らないように食事を心がける必要があります。
1日の消費エネルギー(kcal)を計算する
一日の消費エネルギーはTDEEといい、細かく計算する場合は、METsというものを用いて、一日に行うすべての運動を計算して活動代謝量を計算して、基礎代謝量に加算して計算します。
METsについてはこちらの厚生労働省のwebサイトにて詳しく記載されています。
METsの表についてはこちらからダウンロードが可能です
しかし、上記のような計算は正直手間もかかりますし、日によって大きく変動する部分でもありますので、もっと大まかな数値が知りたいところです。
その場合は以下の簡易的な式の利用がおすすめです。
自身の活動レベルに合わせた数字を基礎代謝にかけて計算してください。
- ほぼ運動しない (基礎代謝 × 1.2)
- 軽い運動 (基礎代謝 × 1.375)
- 中程度の運動 (基礎代謝 × 1.55)
- 激しい運動 (基礎代謝 × 1.725)
- 非常に激しい (基礎代謝 × 1.9)
上記の式はこちらのwebサイトでも計算可能です。



僕は週3~5回の筋トレをしているのと、職業上患者さんと一緒に運動することも多いので、
活動レベルとしては中等度の運動となり、TDEEは2,862kcalとなります。
ここで計算した結果が一日の生活で消費するエネルギーです。これよりも多くエネルギーを摂れば体重は増えますし、少なくすれば体重は減るということになります。
ダイエットの場合は、この計算結果よりもエネルギーを低くすれば良いというわけです。
摂取するカロリーを決める
一日の消費エネルギーの計算ができれば、次に、一日どれくらいのエネルギーを摂取するかを決めていきます。
ここで重要となるのは減量のペースです。
いつまでに痩せたいのか?1か月にどれくらい痩せたいのか?によってここは変わってくるところですが、ここは多くても1か月に3kgくらいを減らすことを目標にするほうが健康面上は良いと思われます。
1か月に3kgの減量を目標とした計算例を示します。
身体の脂肪を1kg減らすために必要なエネルギー消費は、おおよそ7200kcalと言われています。
つまり、1ヶ月で3kgのペースでの減量を目指す場合、1ヶ月をおおよそ30日とすると10日で1kg減らすペースとなります。
体重1kgを減らすには7200kcalの消費が必要なので、10日間で消費エネルギーが摂取エネルギーよりも7200kcal上回るように設定をする必要があります。
つまり、1日あたり720kcal、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回る設定にすればよいということです。



僕のTDEEは2,862kcalですので、1か月に3kgのペースでのダイエットを目標とするなら、
1日あたりの食事から摂るエネルギーは2142kcalまでに抑えればよいということですね!
PFCバランスを決める
1日の摂取エネルギーを決めたら、最後にその内訳、タンパク質と脂質、炭水化物の三大栄養素をどうとっていくかを決めます。
なお、そもそも三大栄養素って何?という方はこちらをご参照下さい
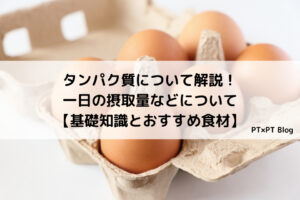
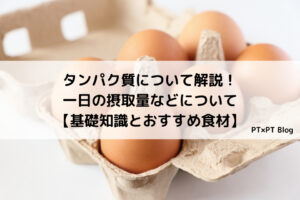
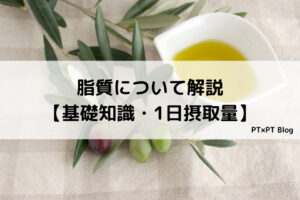
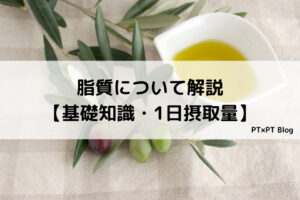
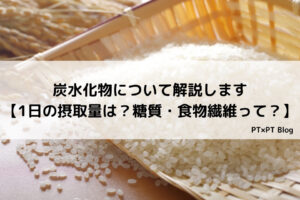
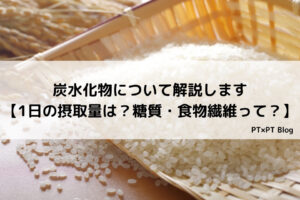
ここで考慮するのは、どういった方法でダイエットをするかです。
自身が取り組みやすい方法に合わせてPFCバランスを割り振りましょう。
タンパク質、脂質、炭水化物をそれぞれ何kcal分摂るのかを計算し終えたら、成分表示などを見て計算しやすいようにそれぞれ何グラム摂ればいいのかに直します。
ちなみに、三大栄養素はそれぞれ1gあたり
タンパク質:4kcal
脂質 :9kcal
炭水化物 :4kcal
です。



僕がローファットダイエットを行う場合は、PFCバランスを3:2:5に設定するとしていて
タンパク質 161g
脂質 47g
炭水化物 268g
が2142kcalの内訳になります。
この制限内で1日の食事をすれば、理論上は月3kgずつ痩せていくということになります。
ダイエットを成功させるためのマインド


最後に、ダイエットを成功させるためにとても大切な考え方をお話します。
かなり僕自身の個人的な意見が混ざっていますので、少し参考にする程度にしていただければと思います。
制限に囚われすぎない
ここまで、カロリー計算や食事のバランスについてお話をしてきましたが、その数値に囚われすぎると、かえってダイエットがうまくいかない場合があります。
もちろん、ボディビルなどのコンテストに出る場合は、大会直前などは特にシビアに神経質に食事を制限する必要があるかもしれませんが、多くの人にとってはそれは当てはまりません。
自分で計算した数値に囚われすぎて、目標の数値よりも多く食べてしまった、少なすぎたなどを一々気にしていてはストレスでかえってダイエットは成功しません。
食べるものまで考えすぎない
ダイエットをしていると、ダイエットに向いている食材やGI値、良質な脂質、食べるタイミングなど様々なワードも耳にします。
もちろん、間違いなくこういったものは効果がありますし、ダイエットを成功に導くのに重要と言えます。
しかし、ただでさえカロリーや栄養素のバランスを気にしているのに、さらに気にすることを増やしてはもうストレスなく食事を摂ることは不可能になってしまいます。
基本的に、何を食べるか、何時に食べるかは無視して大丈夫です。
ケーキを食べようがジャンクフードを食べようが、設定した計算範囲内なら何をしても構いません。
ただし、食事を1日一回にして一食で一日分を食べ切ってしまおうということは消化吸収や健康面の観点からやめておきましょう。



僕自身、体脂肪率が二桁を切るまでは平気で揚げ物やポテトチップスなどのスナックを食べますし、
仕事やトレーニングの都合上夕食が22時ごろになってしまうこともありましたが、
計算したPFCの範囲内で収めることができれば、ダイエットに影響は全くありませんでした。
もちろん、夜の糖質を控えるなんてこともありません。
計算の範囲内なら、お菓子やジャンクフードを食べてもダイエットは成功します。
それってとても気が楽になりませんか?
まとめ:ダイエットはまずは計算、後は気楽に


このブログでは、上記のようにフィットネスやダイエット、食事などに関連した内容を、医療従事者(理学療法士)兼パーソナルトレーナーの目線からお伝えしていきます。
他の記事も是非、ご一読ください。
今回は、以上です。
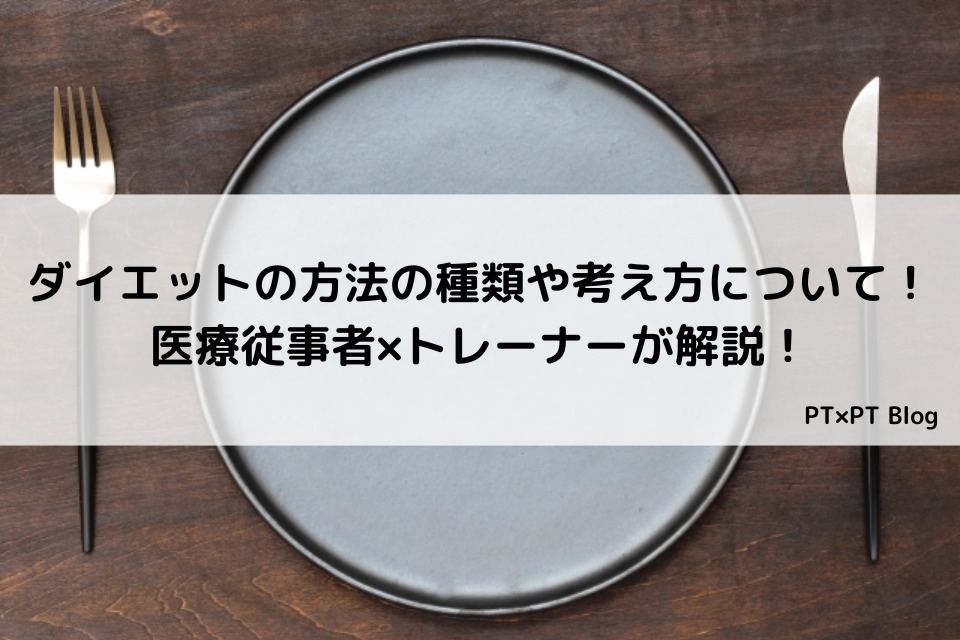

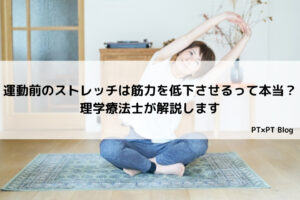
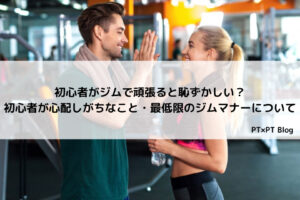
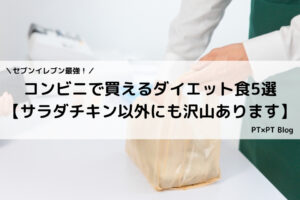
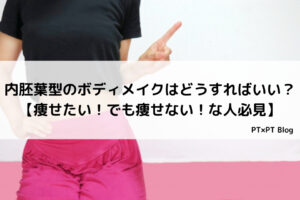
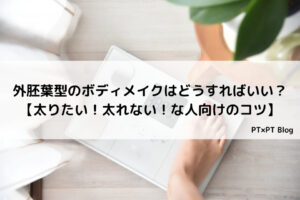
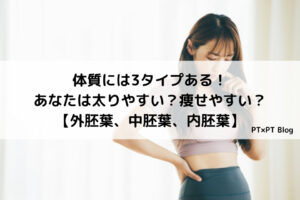
コメント